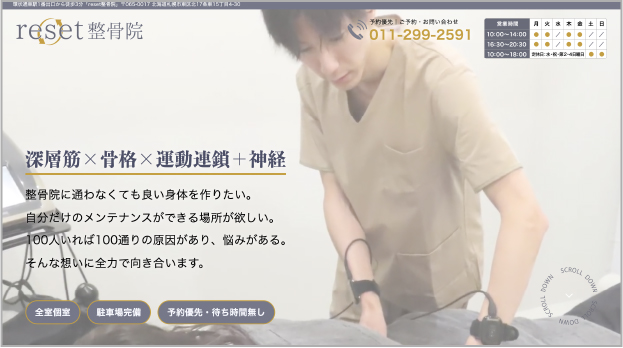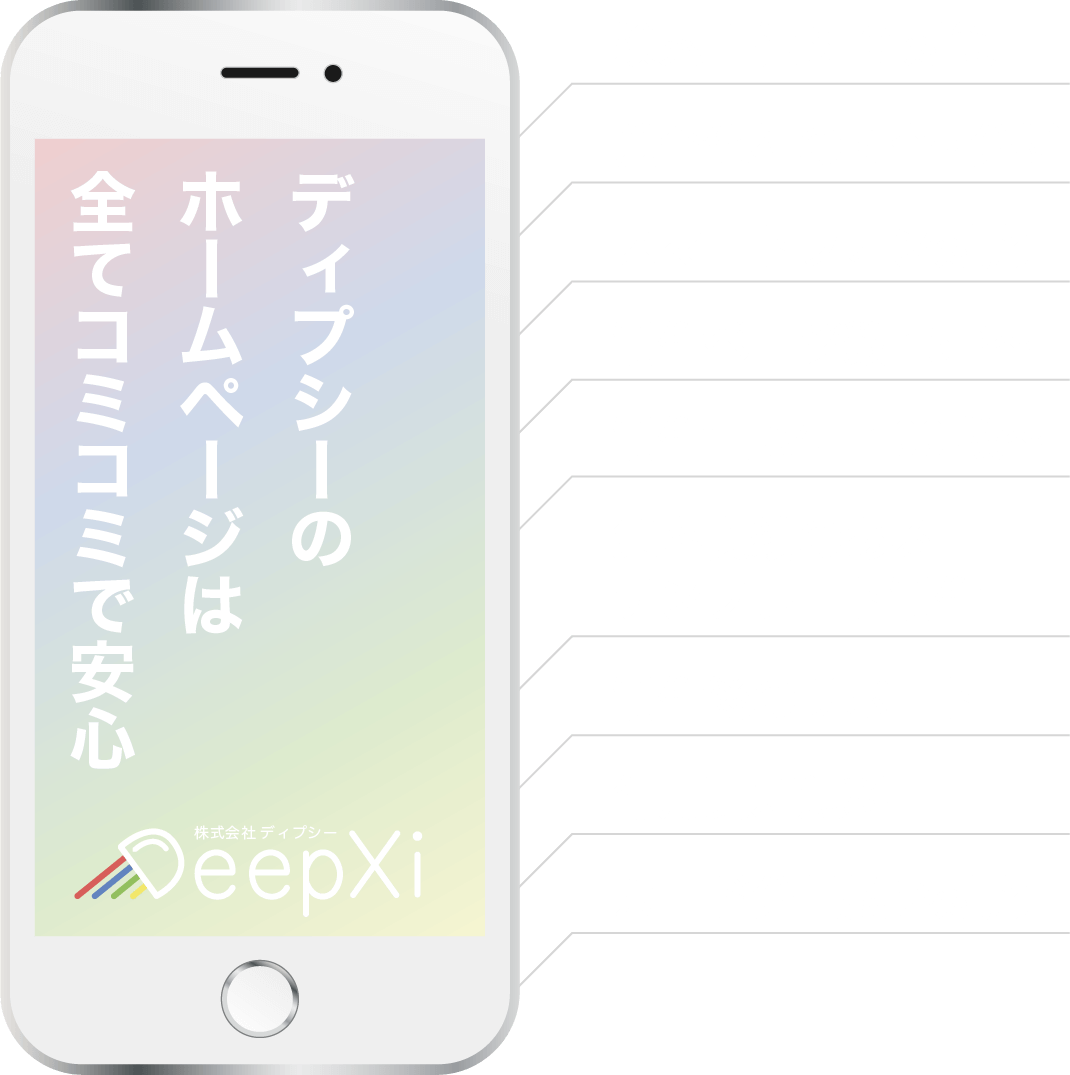「なぜ廃業するのか?」という質問が、柔道整復師や整骨院関係者の間で頻繁に聞かれるようになりました。整骨院は全国に約50,000店舗。コンビニの数55,000店舗とほぼ同数です。さらに新規開業数が年間約3,000店舗ほどある一方で、この数年、同じくらいの数の整骨院が静かに看板を下ろしているのが現実です。「技術があれば食べていける」「国家資格だから安心」という神話はもはや崩れ始めています。
本記事では、ネットマーケティング専門家として整骨院・接骨院・鍼灸院・整体院の専用ホームページ制作で高い実績を誇るディプシーが、廃業に至る具体的な要因を整理し、回避・再生のヒントを解説します。
- 【この記事を読んでほしい人】
- 整骨院の開業を検討している柔道整復師の方
- 患者数減少に悩む現役の整骨院経営者
- 整体・接骨業界への参入を考えている企業担当者
- 通院先の整骨院が閉院してしまった患者さん
- 整骨院経営の将来性を知りたい投資家・金融関係者
整骨院はなぜ廃業してしまうのか?

まず業界全体の状況を把握するところから始めましょう。
厚生労働省の令和4年度「衛生行政報告例(就業医療関係者の概況)」によると、2022年末時点で「柔道整復の施術所」は50,919か所(前回比+555か所、+1.1%)と報告されています この数値は、2012年(平成24年度)の42,431か所から約8,500か所、20%の増加にあたります。業界人口に対して整骨院数の伸びが特に著しいことが読み取れます。
また、公的な統計データではありませんが、業界専門メディアや支援サイトの調査によると、開業後3年以内に廃業する整骨院は約30%、5年以内では50%を超えるとする報告があります(MANAGEMENT COMPASS)。
さらに特に整体業態を含む治療院市場では、開業5年以内に95%以上が閉店するとの推計もあり(全国柔術整鍼灸協働組合)、継続できるのはごく少数とされています。
整骨院が廃業に至る12の理由

私たちが数多くの整骨院の支援をする中で見えてきた廃業パターンを、12の具体的な理由として整理しました。これらは通常2~3の要因が重なって廃業に至りますが、重要なのは、どれも事前に察知し、対策を講じることが可能です。自院の状況と照らし合わせてみてください。廃業要因を知ることで、逆に成功への道筋も見えてきます。
理由1:業界の供給過多と競争激化
なぜ整骨院が廃業するのか、その最大の要因は供給過多による競争激化です。
前述の通り、全国の整骨院数はコンビニとほぼ同数まで増加しています。特に都市部では、半径500メートル以内に5店舗以上の整骨院が存在する地域も珍しくありません。
柔道整復師の養成校が大幅に増加したことで、毎年約6,000人の新しい有資格者が増えます。開業するのはその約半数としても、年間約3,000店舗が新規開業するわけです。しかし、市場規模は横ばいから微減傾向にあるため、パイの奪い合いが激化しているのです。
商圏の重複も深刻な問題です。
同じエリアに複数の整骨院が集中すると、一人当たりの患者数は必然的に減少します。
特に駅周辺や商業施設近くでは、わずか数十メートルの距離に複数の整骨院が乱立していることすらあります。
理由2:保険収入への過度な依存
保険診療への過度な依存も、整骨院廃業の大きな要因の一つです。
療養費制度の改正により、レセプト審査が年々厳格化されています。以前は比較的通りやすかった請求も、現在では詳細な検査結果や症状の記録が求められるようになりました。
保険点数の引き下げも経営を圧迫しています。初回施術料、再検料、後療法料などの報酬単価は、物価上昇に反して据え置きまたは減額される傾向にあります。一回の施術で得られる保険収入は300~800円程度と、美容院やマッサージ店と比較しても極めて低い水準です。
さらに、保険適用範囲の明確化により、慢性的な症状への継続的な施術が困難になっています。腰痛や肩こりなどの症状で長期間通院していた患者が、保険適用外となってしまうケースが増加しています。
理由3:自費診療への移行の遅れ
上記のように保険収入の限界が明らかになる中、自費診療への移行が遅れた整骨院は廃業リスクが高まります。
自費診療では一回の施術料を3,000~8,000円程度に設定できるため、少ない患者数でも経営を安定させられます。
しかし、多くの整骨院が「保険が使えるから来院している患者に、急に自費診療を提案するのは難しい」と考え、移行を先延ばしにしています。その結果、保険収入の減少に対応できず、経営が悪化してしまいます。
自費診療への移行には、施術メニューの見直し、価格設定の検討、患者への説明体制の構築など、多方面での準備が必要です。これらの準備を怠った整骨院では、中途半端な自費診療導入により、既存患者の離脱と新規患者獲得の両方に失敗するケースも見られます。
理由4:ターゲット・コンセプトが曖昧
「何の整骨院なのか分からない」状態は、廃業への道を早めます。
スポーツ障害専門なのか、高齢者のケアが得意なのか、美容系の施術に力を入れているのか、明確なコンセプトがない整骨院は患者から選ばれにくくなります。
特に開業したばかりの院では、「とりあえず何でもやります」というスタンスを取りがちです。しかし、専門性が見えない整骨院は、患者にとって「他との違いが分からない」存在になってしまいます。
ターゲットが曖昧だと、マーケティング戦略も立てられません。どの年齢層に向けて、どのような症状に対して、どのような価値を提供するのかが明確でなければ、効果的な集客は不可能です。
理由5:立地選定のミス
立地選定の失敗は、整骨院経営にとって致命的な問題です。
家賃の安さだけを重視して、駅から遠い、人通りの少ない、視認性の悪い場所を選んでしまうケースが後を絶ちません。
特に問題なのは、同業他社が密集している地域での開業です。既に3店舗以上の整骨院がある商圏に新規参入しても、よほどの差別化要素がない限り成功は難しいでしょう。 また、車でのアクセスが前提の立地でありながら、駐車場のない整骨院も廃業リスクが高くなります。患者の多くは身体に痛みや不調を抱えているため、公共交通機関での通院が困難な場合も多いためです。
理由6:集客・宣伝が弱い
デジタル時代にも関わらず、チラシやポスティングに依存した集客を続けている整骨院は、廃業の危険性が高まります。
現在の患者の多くは、整骨院を探す際にまずインターネットで検索します。Googleマップでの検索結果や口コミ評価が、選択の決め手となることがほとんどです。
WEB集客への対応不足は深刻な問題です。ホームページが存在しない、あっても情報が古い、スマートフォン対応ができていない整骨院は、新規患者の獲得が困難になります。
SEO(検索エンジン最適化)やMEO(マップエンジン最適化)への理解不足も、集客力低下の要因です。地域名と「整骨院」のキーワードで検索された際に、上位表示されない整骨院は存在しないのと同じです。
理由7:口コミ・評判管理ができていない
Google口コミやSNSでの評判管理ができていない整骨院は、ネガティブな情報が拡散されやすくなります。
一つの悪い口コミが、数十人の潜在患者を遠ざける可能性があります。
口コミへの対応も重要です。良い口コミには感謝の返信を、悪い口コミには誠実な対応を示すことで、第三者が見た際の印象を大きく改善できます。しかし、多くの整骨院では口コミ管理が後回しになっています。
SNSでの情報発信も現代では必須です。施術の様子、健康に関する情報、院内の雰囲気などを定期的に発信することで、親しみやすさと専門性をアピールできます。
理由8:経営・会計の知識不足
技術者としては優秀でも、経営者として必要な知識が不足している柔道整復師は少なくありません。
売上だけを見て安心し、固定費・変動費・原価の概念を理解していない経営者は、知らないうちに赤字経営に陥ってしまいます。
損益分岐点の把握ができていない整骨院では、何人の患者を獲得すれば黒字になるのかが分からないまま経営を続けています。これでは効果的な経営戦略を立てることは不可能です。
キャッシュフロー管理の軽視も問題です。売上が上がっていても、入金のタイミングと支払いのタイミングがずれることで、資金ショートを起こす整骨院もあります。
理由9:初期投資や運転資金の見誤り
開業時の初期投資配分を誤る整骨院は、その後の経営で苦労することになります。
内装や設備に予算を使いすぎて、運転資金や集客費用が不足してしまうケースが典型例です。
特に高額な医療機器の導入に傾倒しすぎる傾向があります。数百万円の機器を導入したものの、それに見合う集客ができず、返済負担だけが残る結果となります。
運転資金の見積もりも甘くなりがちです。開業直後から黒字になることはほとんどないため、最低でも6か月~1年分の運転資金を確保する必要があります。しかし、多くの開業者がこの資金計画を軽視しています。
理由10:顧客体験・接客品質の軽視
整骨院はサービス業であるという認識が不足している経営者は、患者満足度を向上させることができません。
施術技術が高くても、受付での対応が悪い、院内が清潔でない、予約が取りにくいなどの問題があれば、患者は他院に移ってしまいます。
特に初回来院時の体験は重要です。問診の丁寧さ、症状への理解度、治療計画の説明、料金体系の明確さなど、すべてが患者の継続通院に影響します。
リピート率の向上に無関心な整骨院では、常に新規患者を獲得し続けなければならず、マーケティングコストが膨らみ続けます。既存患者の満足度を高めることで、リピート率と口コミによる紹介率を向上させることが重要です。
理由11:人材不足・スタッフ離職
スタッフの教育制度が整っていない整骨院では、せっかく採用した人材が定着しません。
技術指導だけでなく、接客マナー、院の理念、患者対応などを体系的に教育する仕組みが必要です。
労働環境の問題も深刻です。長時間労働、休日出勤の常態化、適正な給与体系の不備などにより、スタッフが離職してしまいます。特に若い柔道整復師は、働きやすい環境を重視する傾向があります。
一人院長の場合、病気や怪我で施術ができなくなると即座に収入がゼロになるリスクがあります。代替スタッフの確保や、院長不在時の運営体制を整備していない整骨院は、突発的な事態で廃業に追い込まれる可能性があります。
理由12:時代変化への対応力不足
DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応が遅れている整骨院は、競争から取り残されます。
予約管理システムの導入、キャッシュレス決済への対応、LINE予約の活用など、患者の利便性を向上させるデジタル化が必要です。
パーソナライズされたサービスの提供も重要です。患者一人ひとりの症状や生活スタイルに合わせた施術プランや健康指導を提供できない整骨院は、画一的なサービスしか提供できません。
業界のトレンドや法改正への対応も欠かせません。新しい施術法の習得、法的要件の変更への対応、業界団体での情報収集など、常に学び続ける姿勢が必要です。

廃業しない整骨院が実践している5つの経営戦略

整骨院が廃業するのはなぜかという理由を理解したら、次は、成功している整骨院が実際にどのような経営戦略を実践しているかを見ていきましょう。当社がサポートしている整骨院の成功事例から、特に効果的な5つの戦略を紹介します。どれも特別な才能や多額の資金は必要ありません。地道な継続と正しい方向性があれば、どの整骨院でも実践可能です。
自費診療へのシフトと単価設計
成功している整骨院の多くは、保険診療から自費診療への段階的な移行を実現しています。単純に保険診療をやめるのではなく、患者のニーズに応じて自費メニューを提案する仕組みを構築しています。
たとえば単価設計では、3,000~5,000円の基本メニューを中心に、8,000~12,000円のプレミアムメニューを組み合わせています。
また、継続通院を促進するための回数券や月額制プランも導入しています。
もちろん患者への移行説明も重要です。
「保険では限界がある症状に対して、より効果的な施術を提供するため」という前向きな理由を丁寧に説明することで、患者の理解を得ています。
地域密着+専門性を打ち出したブランディング
成功する整骨院は、地域との密接な関係を築きながら、特定の分野での専門性を確立しています。
例えば、地元のスポーツチームのサポート、高齢者向けの介護予防教室、産後ケア専門など、明確な特色を持っています。
地域イベントへの積極的な参加、健康講座の開催、地元企業との連携など、地域コミュニティとの接点を増やすことで、認知度と信頼度を向上させています。
専門性のアピールでは、院長の経歴、取得資格、研修参加歴などを効果的に発信しています。また、特定の症状に対する豊富な改善事例を蓄積し、説得力のある情報提供を行っています。
WEBマーケティングと口コミ戦略
デジタル時代に対応した整骨院では、WEBマーケティングに戦略的に取り組んでいます。
SEO対策により地域検索での上位表示を実現し、Google マイビジネスの最適化で来院につながる情報発信を行っています。
当社が制作を手がけた整骨院専用ホームページでは、患者の検索行動を分析した構成により、高いコンバージョン率を実現しています。症状別のランディングページ、料金の明確な表示、予約フォームの最適化などが効果を発揮しています。
口コミ戦略では、満足度の高い患者に積極的にレビュー投稿をお願いし、良い口コミを継続的に獲得しています。また、口コミ内容を分析して、サービス改善につなげる仕組みも構築しています。
PDCAサイクルを回す経営管理
廃業しない整骨院では、月次の売上分析、患者数の推移、リピート率の測定など、数値に基づいた経営管理を徹底しています。
単なる売上だけでなく、新規患者数、継続患者数、平均単価、原価率などを細かく把握しています。
改善活動も計画的に実施しています。例えば、初回来院から2回目来院までの期間短縮、問診票の改善、施術メニューの見直しなど、具体的な課題に対して仮説を立てて改善策を実行しています。
スタッフとの情報共有も重要です。月次の数値報告、改善目標の設定、成果の評価などを通じて、院全体で経営改善に取り組む体制を整えています。
定期的な顧客分析・スタッフ教育の実施
患者データの分析により、どのような患者が継続通院するのか、どの施術メニューが効果的なのかを把握しています。
年齢層、症状、来院頻度、満足度などを総合的に分析し、ターゲット戦略の精度を高めています。
スタッフ教育では、技術研修だけでなく、接客マナー、コミュニケーション技術、院の理念浸透などを定期的に実施しています。外部研修への参加も積極的に支援し、スタッフのスキルアップを図っています。
患者満足度調査も定期的に実施し、サービス品質の向上に努めています。アンケート結果をもとに、待ち時間の短縮、院内環境の改善、新メニューの開発などを行っています。

廃業から再起した成功事例

たとえ廃業の危機に陥っても再起は可能です。一度失敗を経験したからこそ見えてくる課題と解決策があり、それを活かして成功を収めている整骨院も実際に存在します。
以下にご紹介する事例は、当社がホームページ制作でサポートした実際の整骨院の再起ストーリーです。失敗の原因分析の重要性、再起に向けた準備期間の活用法、そして成功のための具体的な改善策をこの事例から学ぶことができるでしょう。
田中院長(仮名、47歳)は、15年間続けた整骨院を2019年に一度閉院しました。
保険診療中心の経営で、療養費制度の改正により収入が激減し、月商が半分以下になってしまったためです。
しかし、1年間の準備期間を経て、2021年に同じ地域で再出発を果たしました。今度は自費診療中心の「姿勢改善専門院」としてリニューアルオープンし、現在では月商150万円を安定して達成しています。
成功の要因は、デジタルツールの積極的な導入でした。予約管理システムの導入により、電話対応の時間を大幅に削減し、施術に集中できる環境を整えました。また、Google口コミの獲得に力を入れ、現在では4.8の高評価を維持しています。
施術メニューも大幅に見直しました。従来の保険診療に加えて、姿勢分析、骨盤矯正、猫背改善などの自費メニューを中心に据えました。一回の施術料は5,000円に設定し、継続通院を促進する3回セット、6回セットのコースも導入しています。
さらに、栄養指導や運動指導も組み合わせた総合的なアプローチを提供し、他院との差別化を図りました。患者からは「ただ施術を受けるだけでなく、生活全体の改善につながる」という評価を得ています。
現在では、月間の新規患者数は20名前後で推移し、リピート率は85%を超えています。廃業の経験を活かし、経営指標の管理も徹底しており、「二度と同じ失敗はしない」という強い意志で経営を続けています。
【まとめ】これから整骨院を開業・継続する人に伝えたいこと
整骨院が廃業するのはなぜかを理解することは、成功への第一歩です。技術だけでは勝てない時代になった今、経営者としての視点を持つことが不可欠です。患者ではなく顧客として接し、継続的な価値提供を考える必要があります。
そして、現在、開業を検討している方には、業界の現実を直視することをお勧めします。
甘い見通しで開業すれば、数年後には廃業の危機に直面する可能性があります。しっかりとした事業計画、十分な資金計画、明確な差別化戦略を準備してから開業に踏み切ってください。
現在経営中の方は、廃業のリアルを知ることで危機感を持ち、早めの改善策実行に取り組んでください。「まだ大丈夫」と考えているうちに、手遅れになってしまうケースも多いのです。
特に重要なのは、デジタル化への対応です。
ホームページの整備、予約システムの導入、口コミ管理など、現代の患者が求める利便性を提供できない整骨院は淘汰されてしまいます。
また、継続的な学習と改善の姿勢も欠かせません。業界の動向、新しい施術法、経営手法など、常に学び続けることで競争力を維持できます。廃業のリスクを知り、対策を講じることが、長期的な成功につながります。
整骨院が廃業するのはなぜかという問いに対する答えは明確です。
原因の大半は「経営視点の欠如」にあります。技術者としてのスキルは高くても、経営者として必要な知識や視点が不足していることが、廃業への道を歩ませてしまいます。
トラブルが起こってから対策を考えるのではなく、事前の対策と定期的な検証を習慣化することが重要です。月次の数値管理、患者満足度の測定、競合分析など、継続的な改善活動が廃業リスクを軽減します。
未来型の整骨院経営を目指し、常にアップデートし続ける姿勢が成功の鍵となります。デジタル化への対応、自費診療への移行、専門性の確立など、時代の変化に柔軟に対応できる整骨院こそが、長期的な繁栄を実現できるのです。


 " alt="治療院が患者を増やす方法の正解 ~集客から定着までの「成果が出る全ノウハウ・会話スクリプト」~"/>
" alt="治療院が患者を増やす方法の正解 ~集客から定着までの「成果が出る全ノウハウ・会話スクリプト」~"/>
 " alt="接骨院・整骨院・整体・マッサージ院がGoogleマップで選ばれる「院 MEO」全手順"/>
" alt="接骨院・整骨院・整体・マッサージ院がGoogleマップで選ばれる「院 MEO」全手順"/>
 " alt="接骨院のホームページ制作料金相場と失敗しない制作会社選びの方法"/>
" alt="接骨院のホームページ制作料金相場と失敗しない制作会社選びの方法"/>
 " alt="“儲かる整骨院”の収益モデルと成功戦略"/>
" alt="“儲かる整骨院”の収益モデルと成功戦略"/>
 " alt="月3万円から始めるPPC広告による整骨院の集客戦略"/>
" alt="月3万円から始めるPPC広告による整骨院の集客戦略"/>
 " alt="治療院経営の完全ガイド:開業から成功までの道のり"/>
" alt="治療院経営の完全ガイド:開業から成功までの道のり"/>